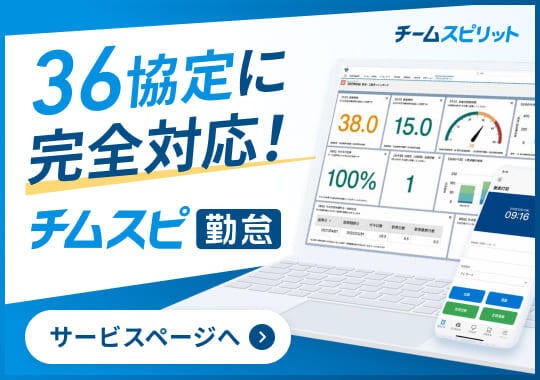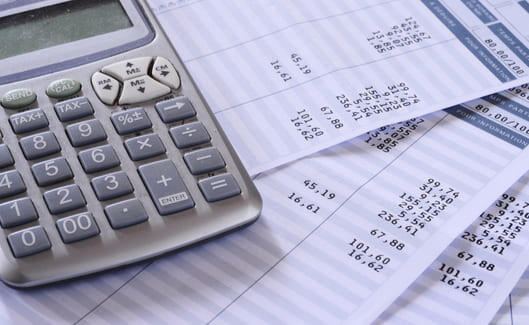休日出勤させる場合の36協定のルールや罰則【社労士監修】
著者:チームスピリット編集部

「法律に則って休日出勤をさせるために、36協定について理解を深めたい」「36協定違反のリスクを避けるため、休日出勤に関する正しい知識を身につけたい」といった課題を抱える企業も多いのではないでしょうか。
法律に則って休日出勤をさせなければ、36協定の違反による罰則やステークホルダーからの評価低下などの問題につながる可能性があります。
本記事では、36協定と休日出勤の関係性、休日出勤をさせる際に注意すべきポイント、36協定違反を防ぐための対策などについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
【36協定を網羅的に解説!】
時間外労働にまつわるルールを無料配布
36協定の正しい理解は、労働法令違反のリスク軽減や、労務トラブル回避、適切な労働管理の把握につながり、従業員の勤怠管理を正しく推進することにつながります。
チームスピリットでは、36協定を始めとした勤怠管理に必要な知識をわかりやすくまとめた「36協定の基礎知識」を無料でお届けしています。従業員の勤怠管理を担うご担当者さまは、ぜひ参考にしてみてください。
「36協定の基礎知識」を無料ダウンロードする目次
36協定と休日出勤の基本ルール
まずは、休日出勤と36協定の関係性について解説した後、基本ルールや関連知識に関して説明します。
法定休日に休日出勤をさせるには36協定の締結が必須
法定休日に従業員を出勤させるためには、労働基準法第36条に定められた「時間外労働と休日労働に関する協定(36協定)」の締結が必須となります。36協定を締結する際には、以下の2つのパターンがあります。
- 労働組合(従業員の過半数で結成)と使用者が協定を結ぶ
- 従業員の過半数の同意のもと選出された代表者と使用者が協定を結ぶ
ただし、管理監督者は代表者になることができず、使用者による代表者の指名も認められていないことに注意が必要です。
協定締結の際は、「協定書」に業務内容や従事する人数など必要事項を記載し、署名・押印を行います。その後、労働基準監督署へ協定書と「協定届」を提出しなければなりません。
協定届には署名・押印は不要ですが、協定書と協定届を兼ねて作成する場合は、署名・押印が必須となります。
▼36協定届の記載例

※引用(PDF):時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)|厚生労働省
なお、36協定は事業所ごとに締結しなければなりませんが、2021年以降、電子申請の場合に限り、企業でまとめて申請できるようになりました。また、詳細は後述しますが、法定休日に出勤をさせる際には割増賃金の支払いが必要です。
※本記事では、便宜上「休日出勤=法定休日(法で休日と定められた日)に労働させること(休日労働)」と解説しています。休日出勤と休日労働の厳密な違いについては後述しています。
管理職は36協定の適用対象外である
36協定は一般従業員を対象とした規定であり、管理監督者に該当する管理職には適用されません。つまり、管理職は休日出勤や時間外労働に関する制限を受けません。労働基準法上では管理監督者は経営者と同等の重要な職務を担当するため、緊急の対応や判断を求められることが多くあるため、36協定締結の適用対象外となっています。
ただし、36協定で定める管理監督者とは、以下の条件を全て満たした管理職のみを指します。
- 職務内容に見合った処遇を受けていること
- 出退勤時間を自らの裁量で決められ、就業規則に定められた勤務時間に縛られないこと
- 経営者と一体化した立場にあり、重要な権限と責任を担っていること
一方、管理職としての実質的な権限や裁量がないにもかかわらず管理職として扱われている従業員、いわゆる「名ばかり管理職」や、役職名は課長や部長などであっても実態としては一般従業員と同様に働く者には36協定が適用されます。
36協定に違反した場合の罰則
36協定は、労働基準法第36条に基づき、使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりするために必要な協定ですが、36協定を作成しなかったこと自体に対する直接的な罰則規定はありません。
しかし、36協定なしで法定休日に休日出勤を行わせた場合、労働基準法第35条で定められた休日のルールに違反したとみなされます。それにより、使用者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という労働基準法第35条の罰則の対象となります。
つまり、36協定を締結せずに休日労働を行わせた場合、労働基準法第36条第1項にも違反していますが、罰則の適用は第35条に基づいて行われるのです。
なお、36協定以外にも以下のような法律・罰則に注意が必要です。
|
違反内容 |
罰則 |
根拠 |
|---|---|---|
|
週に1回(または4週に4回)以上の休日を与えなかった場合 |
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
労働基準法第35条違反 |
|
休日出勤の割増賃金の未払い |
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
労働基準法第37条違反 |
|
就業規則に休日の記載がない場合 |
30万円以下の罰金 |
労働基準法第89条違反 |
休日出勤と「法定休日」「法定外休日」の関係
休日出勤とは企業が休日と定めた日に労働させることをいいます。ただし「休日出勤」には「法定休日」の労働と「法定外休日」の労働の2種類があり、それぞれ36協定との関係や割増賃金の考え方が異なります。
休日出勤と36協定の関係について理解するには、「法定休日」と「法定外休日」の違いを押さえることが不可欠です。本章では休日出勤に関する基礎知識・関連知識の解説をしていきます。
法定休日とは
法定休日とは、使用者が従業員に対して付与しなければならない休日のことを指します。法定休日に従業員を出勤させる場合は必ず36協定の締結が必要で、休日労働の割増賃金が発生します。
労働基準法により、使用者には、「1週間に1回以上または4週間に4回以上の休日を従業員に与えること」が義務付けられています。
法定休日は特定する必要はなく、回数や取得のタイミングが正しければ問題ありません。しかし、週の労働時間の上限規制の関係で、多くの企業では週休2日制を採用しているのが実態です。
法定外(所定)休日とは
法定外休日とは、会社が独自に定めた休日のことで、36協定における休日出勤には該当しません。
労働基準法上は、最低でも1週間に1回の休みを与えれば問題ありませんが、実際には多くの企業が週休2日制を採用しています。その理由は、労働基準法上、週の労働時間の上限は40時間と規定されていることにあります。法定外休日を設定することで、週の労働時間が40時間を超えないように調整できるのです。
法定外休日に労働をさせた場合は、36協定における休日出勤には該当しないため、休日労働としての割増賃金は発生しません。ただし、時間外労働をさせた場合には割増賃金率25%以上の割増賃金の支払いが適用されます。
労務管理を行う際は、法定休日と法定外休日の違いを理解し、混同しないように注意が必要です。両者を正しく区別することで、適切な賃金の支払いが可能になります。
休日出勤と休日労働の違い
36協定の休日出勤に関する規定を理解するには、「休日出勤」と「休日労働」の違いを押さえておくことも重要です。それぞれの意味の違いは以下の通りです。
|
休日出勤 |
企業が休日と定めた日に労働させること(①②両方を含む) ①法定休日の労働(36協定の締結および35%以上の割増賃金が必要) ②法定外休日の労働(36協定の締結は原則不要で、休日労働の割増賃金はなし) ※ただし②において、労働時間が週40時間を超える場合に出勤させる際は、36協定の締結が必要 |
|---|---|
|
休日労働 |
法定休日(法で休日と定められた日)に労働させること(上記の①に該当) ※36協定の締結および35%以上の割増賃金が必要 |
※本記事では、便宜上「休日出勤=法定休日(法で休日と定められた日)に労働させること(休日労働)」と解説しています。
「休日出勤」という言葉は、従業員からすると「通常なら休みの日に出勤すること」という広い意味で使われます。その文脈では法定休日(例えば日曜日)も、法定外休日(例えば土曜日や祝日)も両方とも「休日出勤」に該当してしまうため、理解が難しくなります。労働者からすれば、土曜も日曜も祝日も、休みであることに違いがないからです。
一方、「休日労働」というのは、労働基準法において、法定休日に労働させることをいいます。そして先述の通り、36協定の締結が必要となるのは、労働者にこの「休日労働」をさせる場合です。
なお36協定において時間外労働の上限は原則として1か月45時間以内となりますが、この45時間に「休日労働」の時間は含みません。例えば、休日が土日祝日の企業で日曜日が法定休日となる場合に、日曜日から土曜日までの1週7日間全て出勤したとします。土曜日と祝日の労働時間は時間外労働として1か月45時間の限度時間にカウントされますが、日曜日の労働時間は休日労働として取り扱い、45時間の限度時間に含めずに考えます。
「休日出勤」「休日労働」と割増賃金の有無
「休日労働」に該当すれば休日労働の割増賃金を支払う必要があり、該当しなければ支払わなくてよいというシンプルな構造となっています。
|
①休日労働に該当(割増賃金が発生) |
法定休日に出勤した場合 |
|---|---|
|
②休日労働に該当しない(割増なし) |
法定外休日(所定休日)に出勤した場合※ 振替休日を予め決めていた場合 管理監督者が休日出勤した場合 |
(※)1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた部分については、時間外割増賃金(割増賃金率25%以上)の支払いが必要
例えば、法定休日が日曜日の場合、休日労働の割増賃金が発生するのは日曜日だけです。

詳しくは以下をご覧ください。
休日出勤とは?休日労働に該当するケース・しないケース(割増賃金の有無)
年俸制・裁量労働制・フレックスタイム制における休日出勤の取り扱いと割増賃金
年俸制・裁量労働制・フレックスタイム制といった、特殊な勤務・給与形態における休日出勤の取り扱いに関しては、以下表をご覧ください。
|
働き方 |
休日出勤の取り扱いと休日割増賃金のルール |
|---|---|
|
年俸制 |
年俸には、休日出勤に対する割増賃金(休日手当)は含まれない。 |
|
・裁量労働制※ ・フレックスタイム制※※ |
法定休日に働かせた場合には休日労働の割増賃金を支払う必要がある。 |
※裁量労働制とは、実働時間が長くても短くても一定時間働いたとして計算される働き方。
※※フレックスタイム制とは、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、始業時間や就業時間などを労働者が自主的に決めて働くことができる制度。
パート・アルバイトや派遣社員も休日出勤には36協定の締結が必要
パート・アルバイトなどの非正規従業員や派遣社員であっても、法定外休日の休日出勤を命じる場合は36協定の締結が必要です。それぞれの注意点や休日出勤のルールについて解説します。
パート・アルバイト・契約社員
非正規従業員であっても、正社員と同様に36協定が適用されます。また休日出勤の取り扱いについても正社員と同様で、1週に1日または4週に4日の「法定休日」を与える必要があります。
割増賃金のルールについても同様です。法定休日に働かせた場合には35%以上の割増賃金を支払う必要があります。1日8時間・週40時間を超える労働をさせた場合には、時間外労働の割増賃金(25%以上)を支給します。
派遣社員
前提として、派遣社員に休日出勤や法定時間外労働を命じる場合には派遣元の36協定の範囲内で行う必要があります。
法定休日に働かせた場合には、休日労働の割増賃金を派遣元が支払う必要があります。1日8時間・週40時間を超える時間外労働の割増賃金に関しても、派遣元に支払いの義務があります。
36協定を締結し休日出勤させる際の注意点
36協定を締結し休日出勤させる際には、以下の事柄に注意が必要です。
- 休日出勤時は、休日出勤の内容に応じた割増賃金を支払う必要がある
- 設定した法定休日に従う
- 代休も休日出勤にカウントする
- 勤怠管理を正確・適切に実施する
- 従業員の負担にも配慮する
それぞれどのような点に注意が必要かの詳細を見ていきましょう。
休日出勤時は、休日出勤の内容に応じた割増賃金を支払う必要がある
従業員が休日出勤を行う際には、休日出勤の内容に応じた割増賃金の支払いが必要です。深夜労働の有無などの条件によって割増賃金の計算方法が異なるため、注意が必要となります。
法定休日に出勤した場合、35%以上の割増賃金率が適用された休日出勤手当を支払わなければなりません。さらに、深夜帯勤務の場合は、25%の深夜割増賃金が加算されるため、法定休日の深夜勤務では合計で60%以上の割増賃金の支払いが企業に義務付けられています。
一方、法定外休日に労働をさせた場合は、36協定における休日出勤には該当しないため、休日労働としての割増賃金は発生しません。ただし、時間外労働をさせた場合には割増賃金率25%以上の割増賃金の支払いが適用され、深夜帯勤務の場合は25%の深夜割増賃金が加算されます。
このように、休日出勤した日が法定休日か法定外休日かによって、割増賃金の発生理由が異なり、計算方法も異なるため、勤怠管理の際には休日の種類を正確に把握し、適切な割増賃金の計算を行うことが重要です。
事前に振替休日を設定していた場合は、休日労働分の割増賃金は発生しない
事前に振替休日を設定していた場合は、休日に出勤したとしてもその日は通常の労働時間とみなされるため、休日労働の割増賃金の対象とはなりません。しかし、振替休日の労働が時間外労働となった場合には、時間外労働分の割増賃金が発生します。
設定した法定休日に従う
36協定を締結して休日出勤させる際には、設定した法定休日を厳守することが重要です。一度設定した法定休日を守らなければ法律違反となるため、業務実態に応じた労働契約を結ぶことが不可欠です。
法定休日の設定方法には、以下の2種類があります。
|
原則休日制 |
週に1回の法定休日を設ける方法で、週休2日制を採用している企業に多く見られる。週休2日のいずれか1日を法定休日とする。 |
|---|---|
|
変形休日制 |
シフト制などで取り入れられる方法で、月の起算日から4週間の間に4日間の法定休日を付与する。 |
代休も休日出勤にカウントする
36協定における休日出勤では、「代休を取得しても休日出勤としてカウントされる」というルールがあり、割増賃金の支払い義務が発生します。
代休とは、休日出勤が行われた後に、特定の労働日を休みにすることを意味します。一方、振替休日は、事前に従業員の承諾を得て休日を設けることを指します。振替休日は36協定上の休日出勤には該当せず、割増賃金も発生しません。
代休と振替休日は似た言葉ですが、36協定上の扱いが大きく異なるため、混同しないように注意が必要です。企業には、これらの違いを理解し、適切な休日管理を行うことが求められます。
勤怠管理を正確・適切に実施する
先述の通り、従業員が法定休日に勤務した場合、以下のように割増賃金が発生します。
|
休日の種類 |
割増賃金率 |
深夜労働をさせた場合 |
|---|---|---|
|
法定休日 |
35%以上 |
割増賃金率が追加で25% |
|
法定外休日 |
時間外労働に対して25%以上 |
そのため、従業員に適正な賃金を支払うためには、法定休日と法定外休日を正確に区別して、一人ひとりの労働時間を正確に把握することが重要です。
特に、職種によって働き方が異なる企業や、従業員数が多い企業では、勤怠管理が複雑になりがちですが、そのような状況であっても正確な勤怠管理を徹底することが求められます。
従業員の負担にも配慮する
ここまで解説してきた通り36協定を締結すれば休日出勤をさせられますが、企業には従業員への安全配慮義務があるため、従業員に過度な負担をかけないよう配慮することも大切です。36協定で定められた範囲内であっても、休日出勤が度重なると、従業員の心身の健康を害する恐れがあります。
加えて、休日出勤の際に振替休日や代休を付与しても、従業員は予定の変更によるストレスを感じることがあります。休日の予定が急遽変更されることで、プライベートな時間が十分に確保できなくなるためです。
従業員のストレスが高まると、仕事の効率が低下したり、離職につながったりするリスクがあります。そのため、企業は従業員の心身の健康にも十分に配慮し、休日出勤の運用を慎重に行うようにしましょう。
休日出勤が36協定に違反しないための対策
最後に、休日出勤が36協定に違反しないための対策を紹介するので、違反を防ぐ上で参考にしてください。
振替休日を与える
休日出勤が36協定の上限回数を超えないようにするには、振替休日を活用することが有効です。振替休日とは、先述の通り、従業員の同意を得た上で、休日出勤の代わりに別の休日を設定することを指します。これにより、休日出勤の回数を36協定の範囲内に収められます。
ただし、振替休日を適切に運用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 就業規則に振替休日に関する規定が明記されていること
- 振替休日を設定する際は、事前に従業員の承諾を得ること
- 週1日または4週4日の法定休日が確保されていること
- 振替先の休日が明確に指定されていること
これらの条件が満たされていない場合、たとえ労働時間や法定休日の付与が適切に行われていたとしても、振替休日は無効となってしまいます。
また、振替休日を設定する際は、必ず代替となる休日を指定し、遅くとも前日までに従業員に通知することが求められます。代替休日は、同じ週でなくても構いませんが、法定休日の確保は必須です。
特別条項付き36協定を届け出る
特別条項付き36協定を締結・届出することで、業務が繁忙な時期や緊急の場合に、通常の上限時間を超えた時間外労働を従業員に行わせられます。
特別条項を適用する際には、以下の上限を遵守しなければなりません。
- 時間外労働の年間上限は720時間(法定休日労働は含まない)
- 時間外労働と法定休日労働の合計時間が月100時間未満であること
- 時間外労働と休日労働の合計時間が、1~6ヶ月の期間でそれぞれの月の平均80時間以下であること
- ⽉45時間を上回る時間外労働の実施は年6回が上限であること
ただし、特別条項の利用が認められるのは、業務量の予測不能な増加などのやむをえない事情がある場合や、緊急事態に限定されます。単に繁忙期であるという理由だけでは、特別条項の適用が認められない可能性が高いため、十分な注意が必要となります。
▼36協定の締結状況による上限時間の考え方
|
36協定の締結状況 |
労働時間の上限 |
|---|---|
|
未締結の場合 |
・1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える残業は不可能 |
|
一般条項を締結している場合 |
・月45時間、年間360時間を上限として残業が可能(法定休日労働を含まない) |
|
特別条項を締結している場合 |
・年6回まで、月45時間を超える残業が可能(法定休日労働を含まない) |
勤怠管理システムで休日出勤の勤怠管理を正確に行う
従業員が休日出勤をする際は、休日労働に対する割増賃金の計算などが必要になるため通常とは異なる勤怠管理が求められます。職種によって働き方が異なる企業や従業員数が多い企業では、勤怠管理が複雑になりやすく、特に管理の負担が大きくなるでしょう。
このような状況で、効率的かつ正確な勤怠管理を行うためには、勤怠管理システムの導入が有効な解決策となります。勤怠管理システムを活用することで、休日出勤を含めた全ての勤怠情報を一元的に管理でき、管理業務の負担を大幅に軽減できます。
勤怠管理システムには、以下のような機能が備わっていることが多いです。
- 従業員ごとの休日出勤の回数や各種労働時間の集計
- 上記に合わせた労働時間の自動計算
- 給与計算システムとの連携
- システム上での休日出勤の申請と承認
- 36協定の上限時間の管理とアラート など
▼機能例:従業員ごとの休日出勤の回数や各種労働時間の集計画面

▼機能例:36協定上限に達していないか直感的に確認できる機能

上記は、休日出勤をさせても問題ないか(労働基準法第36条の規定上限に抵触していないか)を確認できるレポート表示機能です。当月の36協定対象の残業時間が40時間を超えたユーザのみを表示させ、40時間以上45時間未満の場合は黄色に、規定上限の45時間を超えたら赤でマーキングされます。
勤怠管理システムを活用して、従業員ごとに休日出勤の管理や賃金計算を行うことで、正確な賃金計算が可能になります。また、システムによる自動計算ができるため、計算ミスを防げるなどのメリットもあり、労働基準法の違反を大きく低減しつつも、業務の効率化も期待できます。
まとめ|休日出勤のルールを守り、36協定の違反を防ごう
法定休日に従業員を休日出勤させるには、36協定の締結が必須です。休日出勤をさせる際は、35%以上の割増賃金の支払いが必要になるなど、法律で定められたルールを遵守する必要があります。企業には従業員への安全配慮義務があるため、可能なかぎり休日出勤を減らして従業員の負担を軽減することも大切です。
36協定の違反を防ぐ上では、勤怠管理システムの活用がおすすめです。他の業務で多忙な中でも、休日出勤の勤怠管理を正確に行えます。勤怠管理システムの選び方については、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
自社に最適な勤怠管理システムをお探しの方へ
- 既存システムでは機能や柔軟性が不足しており、その課題を解決したい
- 就業規則の変更や法改正に都度対応できるシステムを利用したい
- 自社に合わせたシステム運用を提案・サポートしてもらいたい
このような企業には、100以上の勤務パターンへの対応実績があり、会社独自の細かいルールや法改正にも柔軟に対応できる勤怠管理システム「チムスピ勤怠」が最適かもしれません。
解決できる課題や運用イメージなどを具体的にまとめた「チームスピリット サービスご紹介資料」をご用意しました。勤怠管理システムの導入をご検討中の方は、まずは一度ご覧ください。
「チームスピリットのサービス紹介資料」をダウンロードする関連する記事